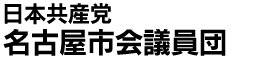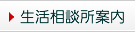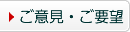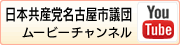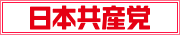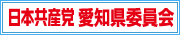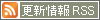愛知県後期高齢者医療広域連合議会2025年8月定例会 一般質問
一般質問(岡田ゆき子議員・2025年8月25日)
1.「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱い」「資格確認証の暫定運用の延長」について
2.「自己負担2割の方の配慮措置終了」について
【岡田議員】
通告に従い、始めに「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱い」について、2点質問します。厚生労働省は、健康保険証の切り替えに伴う対応について、8月4日に事務連絡を出しました。事務連絡は、8月以降、医療機関の窓口で、有効期限が切れた紙の保険証を提示しても、全額自己負担ではなく、一定の負担割合で受診ができるように、来年3月まで暫定的に医療機関等に対応をお願いするというものです。すでに、紙の保険証は7月末で有効期限が過ぎており、マイナ保険証の所有の有無にかかわらず、7月には全員に資格確認書を送付しています。そのうえで、さらに事務連絡が出されたわけですが、本来、法令上は、資格情報は、有効期間内の保険証、昨年12月以降は、マイナ保険証によっての確認が義務づけられていますが、マイナ保険証のトラブルやマイナ保険証が取得できない方もあることから、現状は、暫定的に「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」で資格確認することにしています。しかし、今回、有効期限が切れた紙の保険証でも受診ができるとした理由は何か、お答えください。また、昨年マイナ保険証が義務化され、紙の保険証廃止によって、高齢者や保険者にどんな問題が起きているのか。広域連合の認識をお聞きします。
次に、資格確認書の暫定運用の延長について、お聞きします。マイナ保険証の利用が相対的に低いことと、自治体窓口での混乱などを理由に、厚生労働省は、この8月から次期更新までの1年間、暫定的に、後期高齢者全員に資格確認書を交付することにしました。従来の紙の健康保険証と同様に、交付する措置を取ったことは、これまで強引に進めてきた健康保険証の廃止という措置の行き詰まりを示していると思います。また、医療現場でのマイナ保険証トラブルは続いています。全国保険医団体連合会が行った全国調査でも、マイナ保険証に関わって、9割の医療機関で何らかのトラブルが起きており、最も多いのは、マイナ保険証の有効期限切れが大幅に増加していること、カードリーダーの接続不良など機器のトラブルも増えていること、資格情報が無効など、制度の根幹にかかわるトラブルが続いています。資格確認書の職権交付は今期のみの暫定的な措置ですが、次期更新時までに、これらマイナ保険証に関わる問題が解決すると考えますか。全員に職権交付する暫定運用を、「当分の間」継続するべきと考えますが、広域連合の認識をお聞きします。
最後に、医療窓口の自己負担2割の方の配慮措置について、お聞きします。2022年10月より、窓口1割負担であった被保険者の一部が、2割負担となる制度改定が行われました。その際、これまでの2倍の負担となることに対し、激変緩和として、3年間の配慮措置が行われました。今年で3年目を迎え、この9月には配慮措置が終了することになります。窓口自己負担割合が増えたことによる影響では、6年度には、保険料の値上げが行われ、又コメの高騰など、様々な物価が高騰する厳しい家計状況があり、さらに、受診の負担は大変重いものであると思われます。年々、医療費が伸びていたにもかかわらず、6年度決算では、一人当たりの医療費が前年からマイナスに転じています。認定2号議案でも指摘しましたが、2割負担に対する配慮措置があったとしても、窓口負担が増えたことで、受診抑制を引き起こしていることは否めないと考えるわけです。そこで、2割負担となった方への配慮措置とはどういうものだったかお聞きします。また、配慮措置終了により、負担への影響がどの程度か、外来受診のみの場合として、1割負担で月額4000円の方、と5000円だった方が、2割負担となった方の場合の、配慮措置を受けての月額負担額と、配慮措置終了後の月額負担額で、どれだけ増えるかお聞きします。3年前と現在では、物価高騰、保険料の引き上げなど高齢者の経済的環境は一層厳しくなっています。広域連合として国に対し、配慮措置の延長を求めるべきだと考えますが、認識をお聞きして、一回目の質問を終わります。
1点目の「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱い」について順次お答えいたします。まず、「暫定的取り扱い」に関する事務連絡は厚生労働省から示されておりその理由については、私どもには分かりかねますが、事務連絡の内容について申し上げます。これによりますと「資格確認書の交付に気づかずに有効期限が切れた被保険者証を引き続き保険医療機関等に持参することが想定される。本事務連絡は、当該者について、「令和7年6月27日付け厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課事務連絡」による国民健康保険の加入者と同様の取扱いとすることを妨げるものではない。」とされています。次に、保険証廃止によって、高齢者などにどんな問題が起きているのかについての広域連合の認識ですが、被保険者証が廃止となった後も、被保険者証に代わる資格確認書を対象者全員に交付しており、事務上特段の問題が起こっているとの認識はありません。
続きまして2項目目の資格確認証の暫定運用の延長についてお答えいたします。当該取扱いは、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向け、デジタルとアナログの併用期間を確保するための暫定的な運用であり、この間に、マイナ保険証の利用促進に努めることが重要であるとされております。現在、国による啓発のほか当広域連合としても周知広報に努めているところです。なお、暫定運用の終了する令和8年8月以降につきましては、国の方針に沿った運用をしていく考えです。
【給付課長】
3点目、自己負担2割の方の激変緩和措置終了についてです。激変緩和措置は、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第2号に規定されている一部負担金百分の二十、が適用される者の高額療養費算定基準について、令和4年1月4日に公布された政令により、特例として施行されたものでございまして、 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの受診分につき、制度改正により窓口負担割合が2割となった方に係る1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えるものでございます。この措置の終了に伴い、制度改正により2割負担となった方の自己負担月額につきましては、1割負担で月額4,000円だった場合は月額8,000円となり1,000円の増加、1割負担で月額5,000円だった場合は月額10,000円となり2,000円の増加となります。この措置について、法令の定める期間が令和7年9月30日までとなっております。これまで当広域連合では、配慮措置の内容や期限についてホームページに掲載するとともに、保険料の納付書に同封する小冊子「後期高齢者医療制度のご案内」に掲載し、被保険者のみなさまに送付するなど周知に努めてまいりました。引き続き、丁寧な説明をおこなってまいりたいと考えております。以上です。
【岡田議員】
答弁いただきましたので、要望と再質問を2点いたします。最初に、資格確認書の暫定運用の期限については、国の方針に従うという答弁でしたが、マイナ保険証の利用率は3割台、7割の方は今も資格確認書、または期限切れの保険証でもいいという今の状況があります。この現状が1年後に解決できるとも思えません。当分の間、資格確認書の職権交付ができるように、国に対し、強く働きかけていただきたいと要望します。国民皆保険の下、マイナ保険証への一本化を強引に進めたことで、混乱を避けるためとはいえ、例外的な取り扱いも、2転3転し、被保険者や医療現場、自治体窓口対応も含め、困惑させていると、これまでも指摘してきました。この点について、広域連合は住民と直接窓口業務を持っていませんから、広域連合としては「事務上特段の問題が起こっている認識はない」と、他人事と思える答弁でした。連合長にお聞きします。広域連合計画では、「資格の適正な管理」と「適切な医療給付」を基本方針とているのですから、マイナ保険証の運用から派生している問題だとしても、広域連合として、オンライン資格確認等について、医療機関や介護事業所等や自治体から、現状の問題、課題を聴取する必要はあるのではありませんか、そうした考えはありませんか。お聞きします。
2点目に、自己負担2割となった方の配慮措置の期限が9月末で終了することについて再質問します。2割負担の方に対する配慮措置が終了することについて影響を聞きました。この配慮措置期限については丁寧に周知するとの答弁ですが、配慮措置がなくなって原則通り2割負担となれば、窓口では、例示いただいた方でも1.14倍~1.25倍の負担増となります。政府は物価高騰対策をまだ何も示していません。本広域連合も加わる広域連合協議会は、厚労省に負担増とならないよう配慮措置について要望はしていませんか。
【管理課長】
「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱い」について1点再質問をいただきました。オンライン資格確認につきましては、後期高齢者医療に限らず国が医療DXを推進するため導入を義務化しているものであり、当広域連合として関係機関に対して独自に現状と課題を聴取する考えはございません。
【連合長】
先ほどの「オンライン資格確認」に関する質問について連合長に答弁を求められましたのでお答えいたします。高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、国はこれらの基盤となる医療DXを推進しているところです。その中でオンライン資格確認は、患者本人の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けることが可能となるなど医療DXの基盤となります。国も、すべての後期高齢者医療の被保険者に対して暫定的に資格確認書を交付するなど適切な医療が受けられるよう取り組んでいるところであります。当広域連合としても、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うメリットを丁寧に伝え、その意義について理解を求めていくため、周知・広報に取り組んでいるところです。
【給付課長】
私から、当広域連合も含む全国後期高齢者医療広域連合協議会より、窓口負担の激変緩和に関する国への要望について、お答えいたします。これまで、令和2年、3年、4年に、「やむを得ず窓口負担を引き上げる場合は、激変緩和措置を講じるなど被保険者に配慮するとともに、十分な周知期間を設け、被保険者へ国による丁寧な説明を行うこと」を、要望しました。その後、令和5年6月には、「3年間の配慮措置の期間経過を見据え、被保険者が安心して受診できる環境の維持・整備を国の責任で検討すること」、令和6年6月には、「短期間のうちに判断基準等の見直しによる2割負担以上の被保険者数を増加させる改定は行わないこと」も、要望しております。そして、令和7年6月には、「令和4年10月から導入された窓口2割負担の影響の分析・評価の更なる検討を行い、広域連合・被保険者等に十分な理解が得られるよう周知等に努めること」を要望しております。以上です。