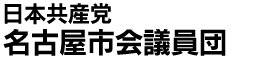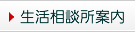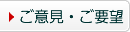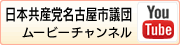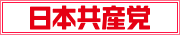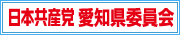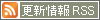愛知県後期高齢者医療広域連合議会2025年8月定例会 議案質疑
令和6年度特別会計決算の認定についての議案質疑(岡田ゆき子議員・2025年8月25日)
【岡田議員】
通告に従い、認定第2号 令和6年度特別会計決算の認定について3点質問します。
一点目は、保険料率の改定についてです。昨年度は、保険料の大幅な値上げが行われ、一人当たりの年間保険料額は103,381円となりました。 まず、保険料率を引き上げた理由、一人当たりの年間保険料の推移と影響額をお聞きします。 次に、保険料の値上げに加え、医療窓口2割負担が導入され、昨年度は2年目迎えた年でもありました。そうした負担増による影響はどうか、医療費への影響をお聞きします。一人当たりの医療費の伸びとその結果に対する認識をお聞きします。2点目に、保険料の滞納について、保険料滞納者の所得階層別人数と被保険者全体に対する割合をお聞きします。 最後に、保険料滞納者に対する差し押さえについてお聞きします。差押え件数、差し押さえた金額、その主な内容と差し押さえを実施している市町村数をお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。
【管理課長】
1点目、保険料率の改定についてお答えします。はじめに保険料改定による影響についてですが、令和6・7年度保険料率改定では、一人当たり医療給付費見込みの増加や、国の医療制度改革により新たに出産育児支援金を負担することになったこと、現役世代の負担上昇を抑えるため高齢者負担率の算定方法が見直され従前の負担率11.72%から12.67%に引き上げられた影響を加味する必要があったため、これらのことを見込むことにより保険料の引き上げを行っております。 なお、一人当たりの平均保険料につきましては、令和5年度が92,060円、令和6年度が105,262円となっており、13,202円増加しています。
2点目の一人当たり医療費の伸びと結果でございます。一人当たり医療費につきましては、令和6年度は986,042円であり、令和5年度の986,585円から543円、0.06%の減少でした。ご承知いただいておりますとおり、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて医療費は減少いたしましたが、その影響による受診忌避が落ち着いた令和3年度以降におきまして、医療費総額および一人当たり医療費は継続して増加の傾向にありました。令和6年度につきましては、このような実績を基に見込みを行ったものでございますが、レセプト1件当たりの医療費が令和5年度に比して減少したこと等から、その見込みより減少したものであると考えております。
続きまして、2点目の保険料の滞納について、令和6年度分保険料に対する滞納者の所得階層及び割合につきましては、基礎控除後の総所得金額になりますが、所得なしが3,497人で同じ所得層の被保険者に対する割合は0.53%、同様に58万円以下が912人で0.64%、200万円以下が2,212人で0.81%、400万円以下が864人で1.40%、600万円以下が130人で0.84%、600万円超えが188人で0.78%となっております。
続きまして、3点目の差し押さえについて、令和6年度の実績としまして、件数は280件、金額は2,226万90円となっております。主な内訳としましては、預貯金が209件で1,542万190円、年金が56件で394万3,696円となっております。なお、実施している市町村数は23市町村となっております。
【岡田議員】
答弁いただきましたので、再質問します。
昨年の保険料を値上げしたのは、医療給付費の見込みの増加と、出産育児支援金を新たに後期高齢者が負担することになったこと、高齢者負担率が引き上げられたことによるとの答弁で、結果平均で1割超える値上げはやむを得なかったという説明でした。 月額で6万9千円弱の老齢基礎年金受給者では、保険料は7割軽減を受けても、改定により年額1200円の値上げとなり、5割軽減の保険料の方でも6800円もの値上げでした。昨年度はさらに、電気、ガス、米代はじめ、物価高が大きな負担となり、負担能力を超える状況があったのではないか、国や県、市町村に真剣に負担軽減のための支援を求めることが必要だったのではないでしょうか。また、さらに深刻と思われるのは、一人当たりの医療費の推移です。コロナ後は増加を続けていたが、6年度は前年に比べて減少していたという事実です。コロナ前の時期も、一人当たり医療費は年々増加の傾向にあったと思います。ですから、一人当たり医療費が減少するということは、これまでにないことであって、医療費2割負担の導入による影響があったと考えられるのではないですか。広域連合の見解をお聞きします。
【給付課長】
令和6年度の一人当たり医療費が減少したことに係る、医療費2割負担の導入の影響につきまして、お尋ねいただきました。一人当たり医療費は、先にお答えしましたとおり、令和3年度以降増加傾向にありましたが、令和6年度は前年度に比してわずかに減少いたしました。しかしながら、医療機関等から保険請求されたレセプトの被保険者一人当たりの年間件数につきましては、令和6年度において31.0件と、前年度の30.9件から増加しております。これは、2割負担が導入された令和4年度(30.7件)からも引き続き増加していることから、当広域連合としてはその影響について判断しかねるところでございます。
【岡田議員】
2割負担導入の影響についてですが、レセプト件数はわずかに増えていることを上げられました。しかし、導入による影響、つまり被保険者の受診抑制を招いているのではないかについては、判断しかねると答弁を避けられました。そもそも、自己負担を増やすことで、受診抑制が起き、結果として医療費が減るという「長瀬効果」を期待した2割負担の導入です。昨年、私がお話を伺った、2割負担となった年金生活者の方が、「薬を間引いて飲んでいる」というお話と2割負担導入した2年目の昨年度決算で、医療費が実際に減少した事実は、連動していると言わざるを得ません。最後に、保険料の滞納、差し押さえについて、再度質問します。保険料滞納者の人数と差押え市町村数を聞きましたが、なぜ滞納となったのか、払えない状況など滞納者の生活実態について、広域連合として把握しているのでしょうか。もう一点、差し押さえを行っている自治体が23市町とのことですが、一方、差し押さえを行っていない自治体が31市町村、半数以上あるということです。名古屋市も差押え件数は多く、そのうち、法定減額を受ける低所得の被保険者の差し押さえが4割超えています。後期高齢者に対する財産差押えの生活に与える影響は大きいと考えます。差し押さえを行なわず、納付相談など努力されている自治体の取り組みを他でも展開する余地があるのではないかと考えますが、最後に見解をお聞きして、議案質問を終わります。
【管理課長】
「滞納者の滞納理由、生活実態等について」お答えします。
滞納処分を含めた収納対策は、市町村事務とされており、文書・電話による催告・来庁のご案内及び、臨戸訪問などにより接触を図る中で、個々の生活状況に即した、きめ細かな収納対策を行っていただいているところであります。広域連合としましては、市町村で対応していただいているすべての状況を把握してはおりませんが、滞納額が高額になるケースなどについては対応状況等を報告いただいているところであり、必要に応じて市町村を訪問し情報共有を図っているところです。
次に「差し押さえを実施していない自治体の取り扱いを展開する考えについて」でございます。差し押さえの実施は市町村が行う収納対策の一つであり、納付相談等を行い、生活状況等を十分に把握したうえで、収入・資産等があるにもかかわらず、なお保険料を納めない被保険者に対して行っているものと認識しており、法令に定められている保険料滞納者に対する措置であります。後期高齢者医療制度の安定した運営のためには、これらの措置を適切に運用する必要があると認識しており、差押えを実施しない取り扱いを、当広域連合から実施主体である市町村に対して展開する考えはございません。